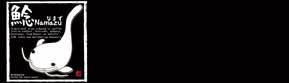全国なまずサミット
埼玉県吉川市の呼びかけで2017年にはじまった「全国なまずサミット」。
このサミットでは、ナマズを活かしたまちづくりに取り組む自治体や関係者が、日本各地のナマズに関する食文化・地域振興・養殖・生態、信仰など、
さまざまな視点から地域ごとのナマズ文化や歴史を発信します。活動の中では、7月2日を「全国なまずの日」として正式に登録するなど、ナマズの魅力を
全国に広める取り組みも進められています。これまでの開催地には、埼玉県吉川市、神石高原町、大川市、行方市などがあります。
(1)参加団体ステージPR
(2)なまずサミット2025宣言
(3)自治体・団体・企業等による展示PRブース
参加自治体・団体・企業等
埼玉県吉川市
岐阜県羽島市
佐賀県嬉野市
広島県神石郡神石高原町
広島県立油木高等学校
福岡県大川市 料亭三川屋
福岡県大川市 大川観光協会
生き物文化誌学会
鯰の民俗文化会
※ なまずサミットのロゴマークは、申請・許可済みです。
なまずサミットの風景 2025・2024年
なまずサミットの風景 2025・2024年
私は2024年からサミットに参加させていただくことになりました。
ナマズにまつわる信仰や風習を広く紹介し、地域振興の発展に貢献していきたいと考えております。
よろしければ、まとめたレポートも併せてご覧ください。
ナマズにまつわる信仰や風習を広く紹介し、地域振興の発展に貢献していきたいと考えております。
よろしければ、まとめたレポートも併せてご覧ください。